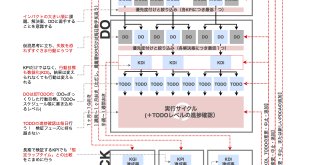photo credit: Eustaquio Santimano via photo pin cc
photo credit: Eustaquio Santimano via photo pin cc
【10年間にも感じられた1年間】
ついに日本を飛び出してから1年がたった。
この1年は溢れんばかりの想い出があり、10年間にも感じられる日々だった。
それだけ、大変なことも多かったし、ぶつかりにいけばいくほど、何度も挫折のようなものを味わった。
逃げるのはいくらでも簡単だった。
【とにかく走り続けた】
経験のない、そう経験のない自分だからこそ、いつも通り目標を明確において走って走って走り続けた。
最初の半年間はとにかくほとんどの朝昼晩、ネイティブの人達とネットワーク拡大しながら関係構築+ビジネスレベルでの語学のベースも構築していった。
居心地のいい日本人コミュニティーをほとんど避け、色んなノン日本人のコミュニティーを時には一晩で3つ以上ハシゴしたりと駆け回った。 会社派遣でのビジネススクールへの留学という違う目的もあったので、そこまでコミットしろと会社から言われてはなかったが、シンガポールのプライベートバンカーのライセンスであるCMFASの必要科目全てを200時間かけて取得し、ダイレクトに顧客とやりとりできるシニアーバンカーとしての地位も確立した。
日本での会社最年少記録の営業成果や経験、そしてシンガポールでの猛スピードでの成果を買われ、全バンカー達の前で1時間ほどのセールス戦略の講演をさせてもらえるほどになった。
その後も、シンガポールの灘高といわれるHWA Chongの卒業生である社会人対象の講演にスピーカーとして招かれたり、その他でも講演に招かれたりすることも増えた。
今だから書けるが、日本でもニュースになったように親しかった先輩の死も経験したし、その後のシンガポールメディアの対応を見ながらメディアやシンガポールという国の裏の世界も垣間見ることができた。
ココロからメンターと呼べるようなシンガポールの経営者達にもお会いできた。
シンガポール政府系企業10社の役員を兼任する重鎮や上場企業創業者達。
そして、この数年シンガポールのベンチャーアワードを総なめする新しい世代の起業家など、多くのメンターに多くの刺激を頂いた。
そういった中で、ある程度形になりビジネスレベルでも通用するようになってからは、その人脈にレバレッジをかけにいった。
自分は「モノゴトを前に運ぶ際に加速度的に速まる、レバレッジが一気にかかるタイミングがある」ことを何度も経験して知っているつもりだ。
分かりやすく言うと、語学なら最低限のコミュニケーションができるようになるとしゃべりまくれるから一気に上達するし、人脈ならある一定まで広がると人脈が新たな紹介を呼び続ける。
これがレバレッジのタイミング。 そこから半年は出張なども多くなってきたりだったが、いろいろな大物に会う事ができた。
それは最初の半年のノン日本人との駆け引きやコミュニケーションレベルを徹底して上げてきた結果だと思う。 ボストンでドラクエ式人生論、Zipcarの顧問として有名な古賀洋吉氏を訪問させて頂いたが、古賀氏の話は本当だと思う。
どんどん強いモンスターを倒して経験値を貯め、レベルアップしていく。この1年もまさにそのような1年だったと思う。
自分じゃ太刀打ちできないようなレベルにどんどん身を置き続け、何度もボコボコにされながら、徐々にそのレベルにこなれてくる。 そのレベルに追いつくために必死で鍛えるしね。
だから、そうやってある程度まで鍛え上げてからは、本当に勝手にアポがうまっていった。
社内外含め、色んな依頼も来た。本当にスケジュールがパンパンになった。
時には、朝から晩まで海外からのゲストのためにVCや政府系機関やビジネスパートナーの紹介などをサポートしたりした。
また時には、土日も朝から晩まで図書館にこもってプレゼン資料なども仕上げたこともあった。(付き合いが悪い事も多く、色々お誘い頂いた方にはお詫び申し上げます。)
そして1年がたった今、これだけは、本当に、心から、そして、自信に満ち溢れて、言える。
「この1年で海外で戦える土台が充五分についた」。
それは語学力なんてもんじゃない、海外の大物達と駆け引きし、想いを伝え、共感する力。
ビジネスアイディアやプレゼン能力でも評価を受ける事ができた。
Singapore Managemnet Universityで行われたスタンダードチャータード銀行主催のビジネスアイディアコンペティションで5人のファイナルリストの1人に選出された。
アジア各国の超エリート達と競争しての結果なので、自分の名前が呼ばれたときは本当に驚いたが、ネイティブや自分よりも遥かに英語レベルの高いメンバーと同じ英語で勝負しても、勝てるってことは結局、伝える力だし、コンテンツってものをどれだけ持ってるかが勝負ってことを最確信させてくれた。
【多くの場所を訪問し、多くのものを見て、多くのことを経験】
こういった最高に充実した1年の中で、シンガポールだけでなく、多くの場所を訪問させてもらった。
多くのことを見ることができた。多くの経験ができた。
異文化が交わるシンガポールのオフィスでは英語はもちろん中国語だけでも北京語・広東語・ホッケンと3種類、日本語も、マレー語も、フランス語やドイツ語まで飛び交っている。
英語ひとつとっても、中国英語・インド英語・欧州英語・イギリス英語・日本英語・シンガポール英語・アメリカ英語など多岐に渡る。
宗教の違いなども経験した、東南アジアの友人やクライアント達はもちろんイスラム教なども多いので、ポークのないレストランなどに気を使わなければいけないし、酒もギャンブルも容易に誘えない。
東南アジアを出張で周っていると建設中のビルがそこら中にあることに成長を肌で実感できたし、四季がない一年中真夏というのも新鮮だった。
欧州人達のドラゴンボートチームに参加していたせいで、ドイツ人が大晦日に絶対見るというDinnerforOneをドイツ人たちと大晦日にビールをガン飲みしながら鑑賞して、そのあと今度はシンガポール人達と年越しの花火見ながらガン飲みし、その後韓国人の友達に合流して、年越しを朝まで祝うみたいな。
チャイニーズニューイヤーでも同じような感じだった。
全部書くのは不可能だが、本当に本当に多過ぎる、そして深過ぎる経験がそこにあった。
きっと、こーいうのは海外留学や帰国子女だったりして、多くの人にとっては、とっくに経験した事もあるんだろうけど、自分は生まれてから2年前までパスポートすら持った事のない、3年前の今はTOEICを本気で解いて375点だったドメドメドメスティックの人間。
本当に全てが新鮮だった。
東南アジアのもちろんインドネシア・マレーシア・フィリピン・タイ・香港・マカオ・ブルネイ・ベトナムなどはもちろん、欧米訪問では6カ国12都市、ロンドン・フランクフルト・パリ・ミラノ・フィレンチェ・チューリッヒ・ルチェルン・ニューへイブン・シカゴ・ワシントンDC・NYC・ボストンと、基本的に会社のバックアップで訪問できたのは本当に大きい。(その代わり社長以下マネジメントチーム+重要ポジション達へのレポート作成は毎回150時間にも渡るスーパータフな作業となりましたが。)
その中で気付いたが、やはりロンドンとNYCってのはやはりレベルが違う。
第一選抜の人間達はここに送り込まれていることに気付いた。
もちろんアジアのハブであるシンガポールと香港も本当に勉強になる場所だ。
アメリカをMelting pot(人種のるつぼ)というが、このような場所も国籍・人種・宗教などのミックス度を考えると十分アジアのハブも対抗しうると感じる。
けど、正直レベルが違うんだ、スピードも人材の質も高い。
欧米の話を続けると、先進国であるイタリアやフランスで経験した物乞いの多さ、イタリアでのスト、宗教の敬虔度の低下、スイスで経験したカルチャーの混合。
ワシントンDCでオバマ大統領の乗ったリムジンに遭遇したり、コネチカットで訪問した世界一のヘッジファンドがグーグルのような社内だったことに驚かされたり、ボストンではハーバードビジネスで行われた、Asia Biz conferenceへも参加させてもらい、多くの次世代リーダー達にお会いしたり、それぞれの場所でいろいろ歴史も感じることができた。
そしてアジアでは、フィリピンやインドネシアやマレーシアのあちこちで見た、ストリートチルドレンの存在。深夜でも服を着ずに外で物乞いに回っている。
自分の夢のひとつである100兆円規模のチャリティーを創出することをココロに誓った。
香港やマカオやブルネイで見た超裕福な世界とバンコクやジャカルタで毎回経験する想像を超える渋滞や貧困さが残る状況など、同じ東南アジアとは考えることができない。
初めて本当に仲良い日本人じゃない親友レベルの仲間が数人出来た、しかもその一人は45歳だ。
日本では年が近い人たちが友人で、それより上の方々は上司やお客さんやメンターや、可愛がってもらってる兄貴的な感じなんだが、海外では本当に同世代かのようなトモダチだ。 いい意味で年齢にあまり気を使わない。
このような経験の中で、そんな世界のトップのアングロサクソン・華僑・印僑などとガチンコで接した中で、なんとなく見えた世界の構造。
アングロサクソンという元々の支配層がいる、彼らは世界大戦を通じてその地位を築き、その後、戦争では手を組んだ、旧ソ連連邦との冷戦にも勝利した。
1990年台、2000年代は彼らの天下で、金融の世界も自由にものにしたのだろう。ただそのアングロサクソンの中でアメリカ軸と英国軸がある。
英国なんてもう金融に頼るビジネスモデルだったので金融危機で終わった国だと思っていた。
しかし、ユニオンヘッドの矢と呼ばれる有名なストーリーがある。
英国・ドバイ・バングロー・シンガポール(香港も含まれることもある)そしてオーストラリアという直線上になる重要な都市(これをユニオンヘッドの矢と呼ぶ)は旧英国圏の国々、もともと英国領であった香港とも近い。
4年に一度行われるCommon Wealth Game(コモンウェルスゲーム)は、彼らにとってオリンピックと同じくらい大事な行事、友好関係を深める絶好の機会。
南アフリカも米国ではなく、英国共同体へ加盟している。
そりゃ、米国が英国との関係を大切にしているのは分からなくもない。
そして、いま現れたアメリカの大敵、中国。
過去のアメリカは市場や情報を操って、中国を制覇することはできただろうが、あそこまで万里の長城ではないが、周囲を鉄壁のバリアで囲った国を制覇するのは難しいだろう。
米国連合(日本はここ)・英国連合・中国といった3強。
クアルンプールへ出張中に中国の温家宝首相と同じホテルになった。
その時、首相は東南アジア外交中、そうやって中国包囲網を形成中であったわけだ。
これから自分は時価総額100兆円企業を創業し、その後総資産規模100兆円の財団を起こすわけだが、こういった世界の構造を無視して進めば、一握りでいなくなってしまうのは当然な話。
そういったときに、「中国に入るのがいいとか悪い」とかという議論は全く筋の通ってない話であることが分かる。
それは、結局どの規模で勝負したいかによって違うだけ。
日本とのブリッジにだけなりたいなら、それは長期に渡って需要はある。
中国の消費者をターゲットにするなら、その人はそれでいい。
しかし、それなりのブランド力があった形で参入しない限り、ローカル化までは時間がかかる。
結局、それはそれぞれのヒトが、どのくらいのダイナミズムとビジネスするかは決める事。
東南アジア各国の役人系のたまご達とはアジアでも欧米でもたくさん会ったが、飲んだり、騒ぎながら、いい関係が築けた。
彼らから東南アジアでビジネスするなら賄賂だ、とはあからさまに言わないがビジネスを拡大するために必要なこともよく学べた。
(※賄賂を贈った訳ではありませんので誤解のないようにしておきます)
うん、世界を少しだけ体系的に見れるようになった気がする。 日能研的に言えば、四角い頭が少し丸くなったかな。
物事をもう少し違った視点から見れるようになって、既成概念を疑うのが得意になった。
これにプラスして世界中の経済を追い続けて、かつ株式や債券などのマーケットでポジションを取り続けて培ったマクロ経済を見る目がフュージョンされると、どんなことが起こるか楽しみだ。
もう既に、その兆候はでてきている、だからビジネスコンペでファイナリストに残ったのだろう。
【人生で一番の出会い】
簡単に上記したが、この1年は死ぬほどぶつかっていったお陰で本当に本当に多くの出会いを経験した。
1年で5回ある2ヶ月に一度の集中講義に参加したビジネススクールではシンガポール政府系の超エリートや、タイ・マレーシア・韓国・中国・インドネシアなどの中央銀行から送り込まれた将来各国の中心になるようなエリート達。
中国の大手金融や中央銀行の幹部が総勢12人参加していたお陰で、中国本土の人脈は主要各地域に張り巡らされた。
一方で、東南アジアを出張や旅行などで動き回れば、ブルネイの王族系やフィリピンの重鎮。 香港では資産1000億円超の台湾タイク-ンや運用資産1兆円のヘッジファンドのトップ。マレーシアでは、首相の右腕と呼ばれる起業家やマレーシア屈指の財閥トップ。
インドネシアではフォーブストップ5の上場企業創業者。
タイでは時価総額タイ内トップ10の上場企業創業者など。
そしてシンガポールでは資産数千億の資産家や上場企業創業者達には多くお会いした。
政府が徹底して学費をかけて養成したシンガポールブレインサイボーグみたいな時期首相候補にもお会いした。
政府系企業10社の役員を兼務する重鎮とも人間関係を構築する事ができたし、 欧米ではUBSの副会長やJPモルガンの幹部、ドコモUSの社長、マッキンゼーのアジア会長など。
そしてなぜかフランクフルトで日銀の白川総裁とレセプションでご一緒し歓談できたなど本当に多くの方々に大物にお会いした。
もちろん日本からのVIPゲストの来客も多かった、上場企業CEO達がこの1年は毎週のようにシンガポールを訪問し、GICやテマセクや他のインベスターへのIRや地元企業とのMTGなどを行った。
時には時価総額数兆円の会長達や社長達まで、本当に多くのそのようなレベルの方々との会食やMTG、時にはBBQなどまでと同席させて頂く事ができた。
その中で多くの刺激も学びもいただく事ができた。
そして、結局簡単な結論に達した。
海外の大物が相手でも結局はちゃんと想いが伝えられるかどうか。
もちろん、最低限も英語を使えなきゃ問題外だが、そこをクリアーしたら結局は、 「あなたのエクスポージャーが何」で、 だから「どんなコンテンツを持ってて、教えてくれるの」で、 「そして何したいの」ってこと。
今後もこのエクスポージャーとコンテンツを厚くし、増やしていきながら、進むべき道を明確に熱く走り続けたいと改めて確信した。